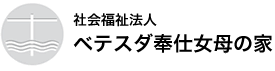社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家について
キリスト教精神に基づいて保育園・女性自立支援施設・就労継続支援B型施設を運営しています。
沿革
| 1935年11月 | 深津文雄牧師が板橋区小茂根町に居を構え、自宅に地域農村の子供たちと日曜学校などの教育活動・茂呂塾を始める。 |
| 1938年 1月 | 茂呂塾日曜学校新校舎落成。 |
| 1938年 4月 | 「茂呂塾幼稚園」開設。定員40名。園長・深津文雄。 |
| 1948年 7月 | 児童福祉法制定に基づき保育所として認可される。 |
| 1949年11月 | ドイツの奉仕女の話を聞いた天羽道子が奉仕女に志願する。 |
| 1954年 5月 | 「ベテスダ奉仕女母の家」創立(館長・深津文雄)。埼玉県加須市の愛泉教会の建物を借りて母の家とし、奉仕女4名の着衣式を行う。 ドイツからの指導奉仕女2名と共に共同生活を始める。 |
| 1954年 6月 | 法人機関誌「ディアコニ」を発刊。(後に「ディアコニア」と改め現在も発行している) |
| 1956年10月 | 「ベテスダ奉仕女母の家」が法人として認可される。 |
| 1956年11月 | 「茂呂塾幼稚園」が「茂呂塾保育園」となる。 |
| 1957年 | 母の家の奉仕女の朝夕の聖想のために、ドイツのヘルンフート兄弟団の「ローズンゲン」の日本語版「日々の聖句」を発刊。(現在も毎年発行している) |
| 1958年 4月 | 婦人保護施設「いずみ寮」を、日本の奉仕女の使命として練馬区大泉学園町に開設。初代寮長・深津文雄。 |
| 1965年 4月 | 婦人保護長期収容施設「かにた婦人の村」を、いずみ寮入所者の願いに応えて千葉県館山市に開設。初代施設長・深津文雄。(後に入所施設と改める) |
| 2014年 6月 | 「かにた婦人の村」から、就労継続支援B型施設「かにた作業所エマオ」を開設。初代所長・佐々木清。 |
いと小さき者と共に
奉仕女(ディアコニッセ)とはプロテスタント教会でディアコニア(奉仕*)に生涯を捧げる女性をいいます。ドイツの牧師フリートナーが創設した制度で、所属する母の家(ムッターハウス)が衣食住を保証してイエスの愛を実践します。ベテスダ奉仕女母の家はわが国初の「奉仕女母の家」です。深津文雄牧師は社会の支援と福祉をつなげる母の家を作り、弱さを抱える人々の傍らに立って生涯を送りました。それを祖とする弊法人は、キリスト教の精神(イエス様の愛に生きる力を与えられた喜びと感謝をもって隣人に仕える)を礎に困難に直面している方々に寄り添います。
*ディアコニア(diakonia)はギリシャ語のdiakonos=奉仕者・仕える者に由来し、キリスト教では「奉仕」を意味します。
ベテスダのロゴマーク
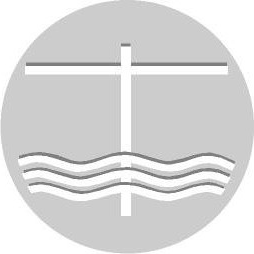
べテスダは恵みの家という意味です。エルサレムの羊の門のそばにベテスダという池があります。天使が池を動かしたときに水に入ると病気が癒される、といわれていました。そこには大勢の病人や盲人たちが横たわっていました。通りかかったイエスが、38年の間病に苦しんでいる人が横たわっているのをごらんになって、病を治してくださったという物語が伝えられています(ヨハネの福音書第5章)。イエス・キリストの癒しを思いださせる十字架とベテスダの池の波、この2つの要素を表しています。
概要
| 法人名 | 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家 |
| 代表者 | 大沼 昭彦 |
| 所在地 | 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町 7-17-30 |
| 連絡先 | 電話:03-3924-2238 WEB:https://www.bethesda-dmh.org |